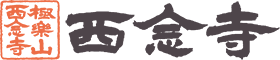2020年西念寺報恩講 法話 海法龍氏(横須賀市長願寺)
常に問い掛けられている存在
このコロナの状況というのは、私たちにとって大変な時期であって、決していいわけではない。感染したら、命が奪われていくかもしれないんです。そういう非常に危険な状況、危機的な状況の中だけれども、逆にコロナ前の生活、それはどうだったのか、本当に良かったのか、どうだったのか。コロナの中、コロナ後、どういう生活、どういう生き方、どういう姿勢で私たちはこの暮らしをしていくのか。そういうことが本当に足元から私たちは問い掛けられているんじゃないか。私たちは問い掛けられた存在です。こういう状況になる前から問い掛けられているわけですよ。
報恩講でもそうです。我々は毎年毎年、この報恩講をお勤めしてますが、報恩講というのは何なのかということですよ。親鸞聖人の教えは自分にとってどうなのかということは、実はいつでも問い掛けられているし、毎日の如く問い掛けられている。だけど、残念ながら私たちは日常の中で、自分の生活の中に障りとか行き詰まりとか感じないと当たり前にするし、当たり前にするとマンネリ化するし、マンネリ化するということはもうただの年中行事でしかなくなります。そこに報恩講の精神がどこかで失われた形で私たちは勤めて来たんじゃないかということが問われますね。もしかすると、この状況の前から私たちは報恩講を死んだものにしてたんじゃないか。コロナの前から、私たちの生活が人間としての在り方というものが、実はもうどこかに失われて、人間そのものが失われて、人間が死んだ形で人間として生きて来たんじゃないか。そういうことも問われてるんじゃないでしょうか。非常に強く感じることでもあります。
「弔う」は「尋ねる」こと
「弔」という字があります。「弔」というのは、今もその言葉はありますけれども、お葬式です。弔う。あまり使わなくなったですね。「弔」の元の言葉があります。古語の「とぶらう(訪)」が「とむらう(弔)」なんですよ。意味は何かと言うと、これは訪問の「訪」ですから、違う漢字で言うと「尋ねる」。尋ねる儀式。亡くなった人の生涯を尋ねる。どう生きたのか。誰にも代わることができない「いのち」を生きた。どういう人生だったのか。そういうことを私たちが尋ねる、そして、そのことを通して自分が今生きてること、これまで生きたこと、これから生きて行くこと、自分の「いのち」ということ、自分の在り方ということもまたそこに尋ねさせられるわけです。
古代中国では人が亡くなると、草むらの上に遺体を安置したそうです。草むらの上に安置すると、月日が経つとどうなりますか。風化して骨になりますね。その骨に向き合う、死者に向き合うという姿が「死」という字だったんです。こっちは残骨、その残骨に向き合う人。膝を折って死者に向き合う。それで、「死」という字になる。だから、亡くなった人がいて、その人に向き合って、その人の人生を尋ねるということがない中で、尋ねること、問い返されるということがない中で、人間の「死」ということは成り立たない。亡くなった人に向き合って、亡くなった人の魂を良い所に、浄土に送るためにお勤めするんじゃなくて、その「死」ということから、私たちが問い掛けられたことをもう一度、お経の言葉に尋ねていかなきゃならない。
草むらでしょう。草むらの上に置いてあるわけでしょう。その下は草なんです。上も草なんです。これは何ですか。これは、葬式の「葬」、そこに阿弥陀様のご本尊様をご安置し、南無阿弥陀仏をご安置し、そしてご荘厳を整えて、お経が読誦されて、そのお経の言葉を皆で分かち合って、そして尋ねていったのが、葬儀、儀式。その私たちの儀式の原点は報恩講。そういうふうにお考え頂いていいんじゃないでしょうか。